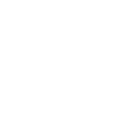患者の皆様へ
patient
「神経伝達物質」、病気そして副作用の関係について(2014年4月掲載)
今日は少し難しいお話をします。精神科で使うお薬の効き方と直結する内容です。
初めに、脳の働くメカニズムについてお話しします。脳は高度で複雑な情報処理をする内臓であることは、皆さん、ご存知だと思います。情報を処理する以上、ある信号のやりとりをすることになります。
この信号の伝わる仕組みには2種類あります。一つ目の仕組みは脳の基本部品である神経細胞内を信号が伝わる仕組みです。この時はイオンの交換が神経細胞の表面で起きて、それにより電気的変化が生じ、それが信号として神経細胞の端から端まで伝わっていきます。神経細胞の端まで信号が伝わり、次の神経細胞へと信号を伝える必要が生じると、二つ目の仕組みが働きます。神経細胞の端からある特殊物質が出てきて、隣の神経細胞の表面にたどり着くのです。そうすると隣の神経細胞は「おー、信号が来たな」と認識し、独自にイオンの交換を始め、自分の端から反対側の端まで電気的変化として信号を伝えて行きます。
このような訳で、脳が信号を正確に伝え正常の働きをするためには、この特殊な物質の働きが非常に重要となっています。この特殊物質を神経伝達物質と呼ぶのです。
この神経伝達物質が必要以上に出過ぎたり、不足してしまうと精神の病気になることがあります。
例えばドパミンという物質が過剰に出過ぎると統合失調症のように幻聴や被害妄想が生じると言われます。セロトニンという物質が不足するとうつ病になると言われます。
脳の中の信号が混乱するわけですから、病気の前とは違ってしまい、本来、その人が健康だったら考えられないような言動となったりするわけです。
ですから、精神科の薬の多くはこれらの神経伝達物質の出方を調節する働きを持ちます。
それにより、脳の中の神経伝達物質の出方が安定すると精神状態も安定し、病気をする前のような生活がこなせるようになるわけです。
ところが、この際に副作用で困ることが多いのも事実です。精神科の薬は非常によく効くことも多いのですが、効き方に個人差が大きいのと、不愉快な副作用が多いとよく言われます。個人差はともかく、副作用の中の一部にやむを得ない副作用があることを最後にご説明します。
少し、具体的な例を挙げて説明します。統合失調症の時にはドパミンが過剰になります。その際にドパミンを抑える働きのある薬(抗精神病薬と言います)を服んでもらいます。そうすると、ドパミンが過剰に働き、病気を引き起こしている部分のドパミンは正常化します。それにより、病気の症状がおさまり、健康な生活が出来るようになります。ここまでは良いことなのですが、この先があるのです。薬は脳全体に行き渡るので病気の部分以外の神経細胞にも効きます。そうすると、病気以外の部分でドパミンの働きが丁度良かった部分のドパミンを下げてしまうので、今度はそのために手のふるえや筋肉のこわばりなどの副作用が生じたりするのです。
つまり、副作用の一部は、本来の薬の働きが目標とする病的部分だけでなく、他の脳の部分にまで及ぶので生じるということになります。このような副作用は本来の薬の働きそのものであり、薬を脳の一部にだけ行き渡らせるのは極めて難しいのでなかなか克服できない現状です。
今回は少しくどくお話ししましたが、精神科の病気と神経伝達物質の関係、薬と神経伝達物質の関係、副作用と神経伝達物質の関係など治療を受ける際に是非ご理解いただきたいことをお話ししました。ご理解いただければ幸いです。