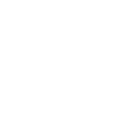部門紹介
guidance
リハセン講座 給食編
当センターの給食について
食べる楽しみ
食事をするということは、ただ単に食べるという事だけではなく、生きていく上での楽しみや生き甲斐となります「冬になるとハタハタが食べたい」「孫と一緒にお寿司を食べたい」など、日常生活の中で、食事は大きな位置を占めます。
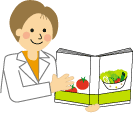



病院での栄養管理の必要性
病院に入院すると、医師からその患者さんに合った食事の指示が出されます。また、2006年度からは、全入院患者さんに栄養管理計画書を作成しています。この計画書とは、患者さんの栄養状態をみるもので、体が低栄養状態だと治療効果が上がらなかったり、リハビリをする体力がなかったりします。また、体に見合った食事をお出ししても、全部食べられず残してしまう患者さんには、低栄養状態にならないように、高栄養食品や高たんぱく質のゼリーなどをお付けしています。
増えている低栄養
栄養状態の判断は、体のたんぱく質の状態、BMI(体格)、喫食率、体重減少率、褥瘡(床ずれ)の有無、貧血の状態などで行っていますが、当センターに入院された患者さんをみると、入院前に大きな手術をしたり、うつ状態で食欲が出なくて食べていなかったりしている方がいて、約8割の方に低栄養状態がみられました。

個人に合わせた食形態
当センターでは、脳卒中後遺症の方や認知症の方など、食事の形態を変えないと食べられない方々がいらっしゃいます。噛めない方には、その方が食べやすい大きさに刻んだり、飲み込みのうまくいかない方にはとろみをつけたり、ブレンダーやムース食など形を変えたり、食事の形態を変えている方が3割です。また、肉が食べられない、魚が嫌いなど、個人に合わせた食事を提供している人が7割を超えています。